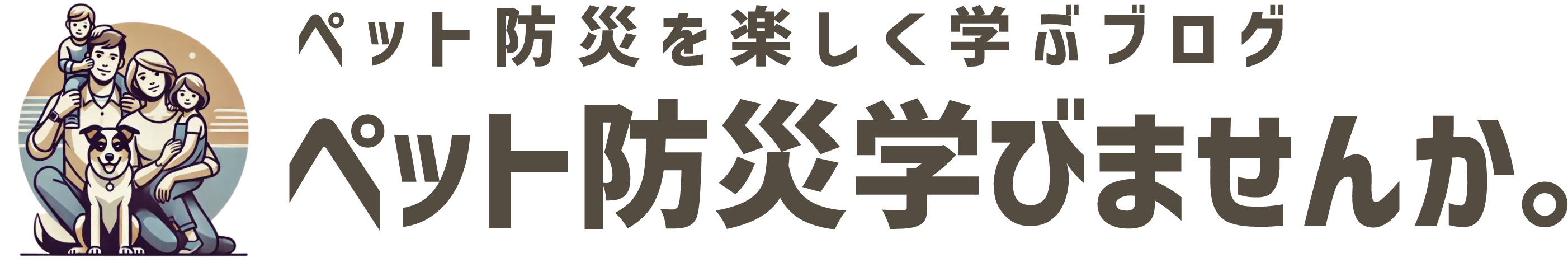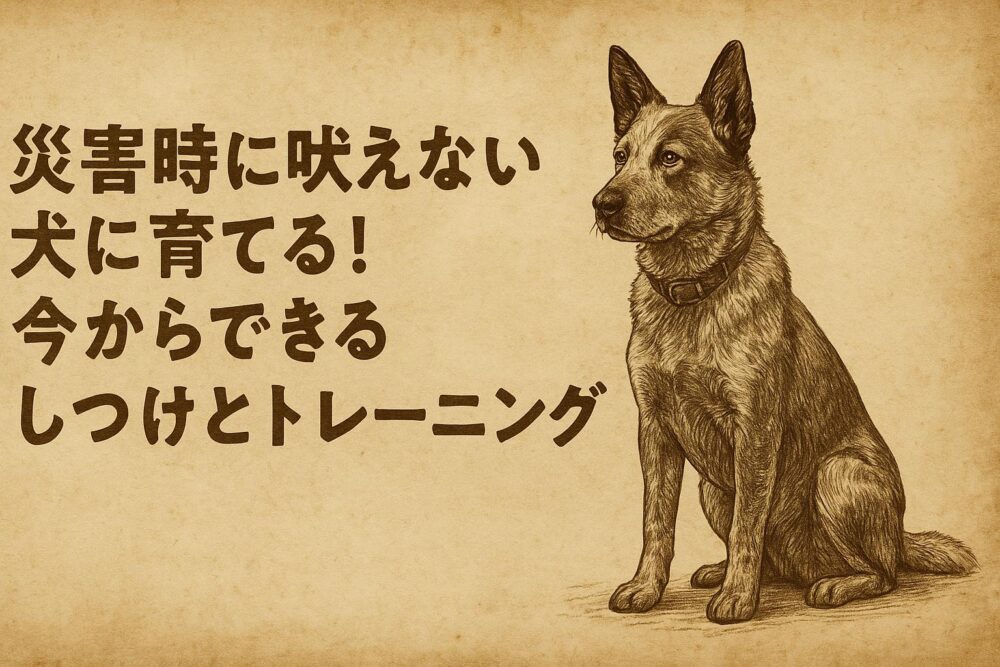地震や台風などの自然災害は、いつどこで起こるかわかりません。そんなとき、大切な家族の一員であるワンちゃんと一緒に避難する「同行避難」が重要視されています。環境省も「ペットとの同行避難」を推奨しており、災害時の備えとして、飼い主さまの意識と準備がますます求められるようになってきました。
しかし、実際に避難所での生活が始まると、多くの人や動物が同じ空間に集まるため、愛犬の「吠える」「落ち着かない」といった行動が問題になることも少なくありません。こうした問題行動が原因で、せっかくの同行避難がうまくいかず、愛犬と離れて避難生活を強いられるケースもあります。
この記事では、災害時に愛犬が吠えずに落ち着いて過ごせるようにするための、しつけやトレーニング方法を紹介します。日常生活の中で無理なく取り入れられる方法ばかりですので、今日からぜひ実践してみてください。
【目次】
- なぜ災害時に犬が吠えるのか?
- 災害時に犬が吠えるとどうなる?避難所での現実
- クレートトレーニングが災害対策の鍵!
- 吠え癖対策|防災にも役立つ犬の無駄吠え対策法
- 社会化トレーニングで“音”や“人”に慣れさせる
- 防災訓練に犬も参加を|避難所体験が最大のしつけ
- まとめ:防災は日常のしつけの積み重ねから
なぜ災害時に犬が吠えるのか?
犬が災害時に吠えてしまう主な理由は、「不安」「恐怖」「混乱」などの強いストレスによるものです。災害という非日常の状況下では、地震の揺れや大きな音、見知らぬ人々、慣れない環境など、犬にとっては未知の刺激が一気に襲ってきます。
また、飼い主さま自身が不安や緊張を感じていると、その気持ちが犬にも伝わり、犬の情緒が不安定になりやすくなります。特に日頃から一人で落ち着いて過ごす練習をしていない犬や、他人や物音に敏感な性格の犬は、より強く反応して吠えたり、暴れたりしてしまう傾向があります。
災害時に犬が吠えるとどうなる?避難所での現実

災害発生後に設置される避難所では、多くの人が不安と緊張の中で過ごしています。そんな中で犬が長時間吠え続けてしまうと、「他の避難者に迷惑がかかる」「子どもや高齢者が怖がる」「眠れない」などの理由で、避難所のスタッフから別の場所に移動するよう求められるケースもあります。
さらに、避難所そのものがペットの受け入れに対応していない場合や、同伴避難はできても「別室管理」になる場合もあります。吠えが原因で避難生活が困難になったり、車中泊を余儀なくされたりすることもあり得るのです。
つまり、災害時に犬が吠えないようにするしつけやトレーニングは、愛犬の命を守るだけでなく、飼い主さま自身の避難生活を支える備えでもあるのです。
クレートトレーニングが災害対策の鍵!
災害対策として最も実用的かつ効果的なのが、「クレートトレーニング」です。クレートとは、プラスチックや布製の持ち運び可能なケージのことで、災害時や移動時に犬の安全と安心を確保するための必需品です。
普段からクレートに慣れておくことで、避難所や車内などの限られた空間でも落ち着いて過ごすことができるようになります。クレートは犬にとって「安心できる自分の巣」のような存在になるため、怖がることなく入ってくれるようになります。
犬のクレートトレーニングが防災に役立つ理由と覚えさせ方について
クレートトレーニングのポイント:
クレートは避難時だけでなく、旅行や病院への通院にも役立つので、ぜひ日頃から活用しましょう。
吠え癖対策|防災にも役立つ犬の無駄吠え対策法
犬の「吠え癖」は、災害時のトラブルを防ぐためにも日常から改善しておきたい課題です。吠えの原因はさまざまですが、代表的なものには以下のようなものがあります
これらの吠えは、一貫したしつけと環境づくりによって徐々に改善することができます。
無駄吠え対策の実践例:
しつけは継続が鍵です。焦らず、日々の積み重ねを大切にしましょう。
社会化トレーニングで“音”や“人”に慣れさせる
災害時は、「音」や「人」「動物」など、犬にとってストレスとなる刺激が一気に押し寄せます。こうした刺激に慣れていないと、恐怖から吠えたり、逃げ出したりするリスクが高くなります。
そのため、日常から社会化トレーニングを行うことが、災害対策にも直結します。
社会化トレーニングのポイント:
「社会化」は子犬のうちからが理想ですが、成犬でも段階的に慣らしていくことは可能です。
防災訓練に犬も参加を|避難所体験が最大のしつけ

最近では自治体や動物団体によって、「ペット同行避難」を想定した防災訓練が行われるようになっています。実際に愛犬と一緒に訓練に参加することで、避難所での実態を飼い主も犬も体感することができ、大きな学びとなります。
避難訓練でチェックすべき項目:
また、非常持ち出し袋の中身や避難所でのマナー確認など、事前準備にも役立ちます。防災訓練は地域での絆を深める機会にもなりますので、積極的に参加してみましょう。
防災は日常のしつけの積み重ねから
災害は予測できませんが、備えることは誰にでもできます。大切なのは、「いざという時のため」ではなく、「いつ起きても大丈夫なように」準備しておくこと。
そのためには、日常の中でのしつけやトレーニングを怠らないことが、最大の防災対策となります。愛犬が安心して避難生活を送れるよう、飼い主さまの手で準備を進めていきましょう。
**愛犬の命を守れるのは、飼い主さまだけです。**今からでも遅くありません。少しずつ、できることから始めてみてください。